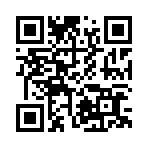2011年07月29日
常に周りに感謝をする
こんばんは、シンプルウェイの大野です。
シンプルウェイという会社を設立してから5年目になりますが、
最近よく感じることがあります。
企業として何かを成し遂げた時に、社会から評価されるのは一般的に経営者です。
取材・インタビューを受けて記事になったりと、どうしても経営者にスポットが当たります。
ただ多くの場合、経営者1人では何も成し遂げられません。
弊社の場合も例外ではなく(むしろ典型)、プロジェクトの企画・管理は私が担当することが多いのですが、デザイナー、コーダー、プログラマー、営業など、たくさんのスタッフの力があって初めてプロジェクトが動きます。
私の担当部分は、プロジェクト全体でみたら本当にほんの一部であるのにも関わらず、プロジェクトがうまくいった場合、どうしても経営者である私にスポットライトが当たると思います。
ではそのような時、経営者としてどのようなことをすればいいのでしょうか。
ボーナスなどの報酬を与えることはもちろん必要ではあると思いますが、感謝の気持ちをスタッフ全員に自分の言葉で心を込めて伝えることが大事ではないかと思います。
それをしなければ、スタッフは会社から気持ちが離れ、次第にパフォーマンスも悪くなり、最悪の場合会社を去ってしまうことも考えられます。
今、弊社では大きなプロジェクトが動こうとしています。
常に関係者への感謝を忘れず、経営者である私が人一倍仕事をして、必ずプロジェクトを成功させたいと思います。
担当:大野
シンプルウェイという会社を設立してから5年目になりますが、
最近よく感じることがあります。
企業として何かを成し遂げた時に、社会から評価されるのは一般的に経営者です。
取材・インタビューを受けて記事になったりと、どうしても経営者にスポットが当たります。
ただ多くの場合、経営者1人では何も成し遂げられません。
弊社の場合も例外ではなく(むしろ典型)、プロジェクトの企画・管理は私が担当することが多いのですが、デザイナー、コーダー、プログラマー、営業など、たくさんのスタッフの力があって初めてプロジェクトが動きます。
私の担当部分は、プロジェクト全体でみたら本当にほんの一部であるのにも関わらず、プロジェクトがうまくいった場合、どうしても経営者である私にスポットライトが当たると思います。
ではそのような時、経営者としてどのようなことをすればいいのでしょうか。
ボーナスなどの報酬を与えることはもちろん必要ではあると思いますが、感謝の気持ちをスタッフ全員に自分の言葉で心を込めて伝えることが大事ではないかと思います。
それをしなければ、スタッフは会社から気持ちが離れ、次第にパフォーマンスも悪くなり、最悪の場合会社を去ってしまうことも考えられます。
今、弊社では大きなプロジェクトが動こうとしています。
常に関係者への感謝を忘れず、経営者である私が人一倍仕事をして、必ずプロジェクトを成功させたいと思います。
担当:大野
2011年07月28日
お金は有限、アイデアは無限

皆さんこんにちは、シンプルウェイの川久保です。
突然ですが、手元に500円玉を渡されて、2時間の間に出来るだけ増やしなさいと言われたら、あなたならどうしますか?
時間のある方は、自分ならどうするか、思いつくアイデアを書き出してみて下さい。
どんなアイデアが浮かびましたか?
「まず、500円をどう使おうか・・」
そこから考え始めてしまった方は、ちょっと頭が固くなってきているかもしれません。
冒頭文と同じ課題(金額は5ドルに設定)をスタンフォード大学の学生に出したところ、成功したチームは持ち金を100倍以上に増やすことができたそうです。
一つのチームは、週末の夜に混み合うレストランの予約を事前に確保し、予約の時間が近づくと、長蛇の列の最後の方で待っている客に対して自分たちが予約した席を売ることで数百ドルを稼ぎました。
これだけでも、「なるほど、よく考えたなぁ…」と感心してしまいますが、一番優秀な成績を修めたチームは、さらに賢い方法で650ドルを稼ぎ出したそうです。
彼らは、自分たちが持っている資源の中で、一番価値のあるものは、5ドルでも2時間でもなく、課題の結果をクラスで発表する3分間であることに気付きました。
スタンフォード大学の学生を採用したい企業を有料で募り、その企業のCMを作成して、この3分間に流すことにより、650ドルを手に入れたというわけです。
課題に成功したこれらのチームは、5ドルには一切手を付けず、自分たちのアイデアのみを元手にお金を稼ぎ出したという点が、とても興味深いですね。
5ドルという金額に縛られず、自分たちが持っている資源を洗い出し、そこからいかに価値あるサービスを考え出せるかが、この課題の重要なポイントであったのです。
アイデア次第で、いくらでも価値を生み出すことができる。
そこがビジネスの一番の難しさであり、一番の面白さなのだなぁと、半年間社会人をしてみてつくづく実感しています。
※参考文献:Tina Seelig著『What I Wish I Knew When I Was 20 ~20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学 集中講義』(阪急コミュニケーションズ、2010年)
担当:川久保
2011年07月27日
挨拶のチカラ
「おはようございます」「おつかれさま」「ありがとう」「いってきます」「お先に失礼します」などなど、
皆さん、家でも職場でしっかり挨拶をしていますか?

以下の文章は「禅語」という本の中にある一節です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
満員電車でぎゅうぎゅうに押しこまれ、互いに体をおしつけ合っていても、私たちは完全に他人でいられる。言葉を交わさない限り、見知らぬ人であり、いわば、壁や物体と変わらない。言葉を交わさない相手は私たちにとって、何の意味も持たない「他人」だ。
けれどもひとたび「こんにちは」と声をかけられた瞬間、その相手は、ほとんどモノから人に変身したように、あざやかに景色の中に浮かび上がって見える。こちらからも返事をしなければならない、力を持った存在に変わる。
挨拶は交わされる言葉そのものにはほとんど意味がない。
「こんにちは」は英語に直訳すれば「today」でしかない。何の用事もない。何の情報もない。でも、「こんにちは」と声をかけられたとき、そこに、私たちは自分にとって何らかの意味をもつ人間の姿を見い出す。その一言に安心やつながりを確かめる。
モノが人に変わるような劇的な変化を、「挨拶」は引き起こすことができるのだ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ものすごく共感しました。
ここで書かれている通り、挨拶はものすごい大きな力を持っていると思います。
さらに、挨拶とは単に言葉を交わせばいいものではなく、「相手の目をみて言葉を交わす」ということがとても大事だと私は思います。
やろうと思えば誰にでもできる、とても簡単なことだと思います。
実践できていない方は、早速今日から実践してみてください。
初めは少し照れくさいかもしれませんが、そうするだけで距離が縮まり、その相手との関係が変わると思いますよ。
※参考文献:石井ゆかり著『禅語』(ピエブックス、2009年)
担当:大野
皆さん、家でも職場でしっかり挨拶をしていますか?

以下の文章は「禅語」という本の中にある一節です。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
満員電車でぎゅうぎゅうに押しこまれ、互いに体をおしつけ合っていても、私たちは完全に他人でいられる。言葉を交わさない限り、見知らぬ人であり、いわば、壁や物体と変わらない。言葉を交わさない相手は私たちにとって、何の意味も持たない「他人」だ。
けれどもひとたび「こんにちは」と声をかけられた瞬間、その相手は、ほとんどモノから人に変身したように、あざやかに景色の中に浮かび上がって見える。こちらからも返事をしなければならない、力を持った存在に変わる。
挨拶は交わされる言葉そのものにはほとんど意味がない。
「こんにちは」は英語に直訳すれば「today」でしかない。何の用事もない。何の情報もない。でも、「こんにちは」と声をかけられたとき、そこに、私たちは自分にとって何らかの意味をもつ人間の姿を見い出す。その一言に安心やつながりを確かめる。
モノが人に変わるような劇的な変化を、「挨拶」は引き起こすことができるのだ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ものすごく共感しました。
ここで書かれている通り、挨拶はものすごい大きな力を持っていると思います。
さらに、挨拶とは単に言葉を交わせばいいものではなく、「相手の目をみて言葉を交わす」ということがとても大事だと私は思います。
やろうと思えば誰にでもできる、とても簡単なことだと思います。
実践できていない方は、早速今日から実践してみてください。
初めは少し照れくさいかもしれませんが、そうするだけで距離が縮まり、その相手との関係が変わると思いますよ。
※参考文献:石井ゆかり著『禅語』(ピエブックス、2009年)
担当:大野
2011年07月26日
「おとな」になることを注意深く拒む

皆さんこんにちは、株式会社シンプルウェイの川久保です。
子供の頃、「大人はどうして分かってくれないんだろう…」と、もどかしい思いをしたことはありませんか?
「私は、大人になっても絶対に子供の気持ちを忘れない。」
幼心にそう誓った私が、20代のはじめ頃から、ある意味教科書代わりに読んでいるのが、サン=テグジュペリ作『星の王子さま』です。
その中に、こんな一節があります。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小惑星B612について、こんなにくわしく話したり、番号まで明かしたりするのは、おとなたちのためだ。おとなは数字が好きだから。
新しい友だちのことを話しても、おとなは、いちばんたいせつなことはなにも聞かない。
「どんな声をしてる?」とか「どんな遊びが好き?」「蝶のコレクションをしてる?」といったことはけっして聞かず、「何歳?」「何人きょうだい?」「体重は何キロ?」「おとうさんの収入は?」などと聞くのだ。
そうしてようやく、その子のことがわかった気になる。
もしおとなに「バラ色のレンガでできたすごくきれいな家を見たよ。窓辺にはゼラニウムがいっぱい咲いていて、屋根にはハトが何羽もいるんだ……」と話しても、おとなはうまく想像することができない。
それにはこう言わなくてはならないのだ。「十万フランの家を見たよ!」するとおとなたちは歓声をあげる。「それはすてきだろうね!」
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
この文章を読むと、なんだかハッとさせられませんか?
物事の価値を表現するとき、たしかに数字は大切な役割を果たします。
ですが、数字はあくまで表現する手段にすぎず、物事の価値そのものではありません。
上の文章を見ると、数字という概念をまだ良く知らない子供の方が、より物事の価値そのものに近い言葉で世界を捉えているのが分かります。
ビジネスにおいても、日常生活においても、数字だけに踊らされるのではなく、純粋に物事を見つめる子供たちのような目で、「本当にその数字で表現されるだけの価値があるのか」をしっかりと見極められる大人になりたいものですね。
※参考文献:サン=テグジュペリ作『星の王子さま』
担当:川久保
2011年07月25日
成功している経営者の共通点に学ぶ
こんにちは、株式会社シンプルウェイの大野です。
これまで、様々な企業のコンサルティングをさせていただいておりますが、成功している多くの経営者の目標には、具体的であり(数値化されている)、かつ達成の期限が設けてある、という2つの大きな共通点があります。
「半年以内に売上を15%アップさせる」などですね。
さらに、そのような経営者の方に「何を何個売って目標を達成させますか?」
という具体的な質問をすると、多くの場合即回答が返ってきます。
1年以内に売上を15%アップさせたい!
→そのためには、Aという商品をこれまでと比べて月に○個多く売らなければならない。
→Aをこれまでと比べて月に○個多く売るためにはどうしたらいいか?
新規のお客様を増やすべきか?リピーターの来店頻度を高めるべきか?
新規のお客様を増やすために…
・インターネット広告をしよう
・○月までにHPを改善しよう
・○月までに新規出店をしよう
リピーターの来店頻度を高めるために…
・今すぐリピーターに手紙(DM)を送ってみよう
・メールマガジンの内容を改善しよう
・新商品発売のタイミングを変えてみよう
常にこのようなところまで考えているということですね。
(経営者としては当たり前だとも言えますが…)
逆に、伸び悩んでいる企業の経営者は、目標が明確でなかったり(数値化されていない)、期限がなかったりするケースが多いように思います。
期限がないということは、達成するまでの人件費等の費用計算ができないため、売上はアップしたけれど、予想以上に費用がかかってしまい利益が減少した、という事態に陥る可能性も高くなってしまいます。
ですので、目標はできる限り具体的であるべきですし、必ず期限を設けるべきです。
限られた時間の中で企業としてどのように行動し目標を達成するか。
その戦略を考えることが、経営者の仕事の中で重要かつ、楽しい部分でもあると私は思います。
何かを改善したいと漠然とお考えの方、何をいつまでにどう改善したいか、できる限り具体的に考えてみてください。やるべきことが明確になり、道が開けるはずです。
どうしてもうまくいかない場合はご相談ください。
現状分析から、目標設定、戦略策定、実行支援までワンストップでお手伝いさせていただきます。
担当:大野
これまで、様々な企業のコンサルティングをさせていただいておりますが、成功している多くの経営者の目標には、具体的であり(数値化されている)、かつ達成の期限が設けてある、という2つの大きな共通点があります。
「半年以内に売上を15%アップさせる」などですね。
さらに、そのような経営者の方に「何を何個売って目標を達成させますか?」
という具体的な質問をすると、多くの場合即回答が返ってきます。
1年以内に売上を15%アップさせたい!
→そのためには、Aという商品をこれまでと比べて月に○個多く売らなければならない。
→Aをこれまでと比べて月に○個多く売るためにはどうしたらいいか?
新規のお客様を増やすべきか?リピーターの来店頻度を高めるべきか?
新規のお客様を増やすために…
・インターネット広告をしよう
・○月までにHPを改善しよう
・○月までに新規出店をしよう
リピーターの来店頻度を高めるために…
・今すぐリピーターに手紙(DM)を送ってみよう
・メールマガジンの内容を改善しよう
・新商品発売のタイミングを変えてみよう
常にこのようなところまで考えているということですね。
(経営者としては当たり前だとも言えますが…)
逆に、伸び悩んでいる企業の経営者は、目標が明確でなかったり(数値化されていない)、期限がなかったりするケースが多いように思います。
期限がないということは、達成するまでの人件費等の費用計算ができないため、売上はアップしたけれど、予想以上に費用がかかってしまい利益が減少した、という事態に陥る可能性も高くなってしまいます。
ですので、目標はできる限り具体的であるべきですし、必ず期限を設けるべきです。
限られた時間の中で企業としてどのように行動し目標を達成するか。
その戦略を考えることが、経営者の仕事の中で重要かつ、楽しい部分でもあると私は思います。
何かを改善したいと漠然とお考えの方、何をいつまでにどう改善したいか、できる限り具体的に考えてみてください。やるべきことが明確になり、道が開けるはずです。
どうしてもうまくいかない場合はご相談ください。
現状分析から、目標設定、戦略策定、実行支援までワンストップでお手伝いさせていただきます。
担当:大野
2011年07月22日
力をくれる言葉たち(『西の魔女が死んだ』ver.)
「シロクマがハワイより北極で生きるほうを選んだからといって、だれがシロクマを責めますか」
『西の魔女が死んだ』という小説、映画化もされたのでご存じの方も多いでしょう。
冒頭の言葉は、イジメが原因で学校に行けなくなった主人公の女の子が、新しい学校に転校するかどうかで悩んでいる時に、おばあちゃんが主人公に対してかけた言葉の一節です。
新しい岐路に立ち、自分で何かを選択しなければならない時、この単純明快な言葉にいつも支えられています。
「北極よりもハワイが良い」という人は沢山いるかもしれませんが、一番大切なのは、他の誰でもない自分にとって、「北極」と「ハワイ」どちらで生きるのが幸せなのかを、しっかりと見極めることなのではないでしょうか。
※参考文献:梨木香歩『西の魔女が死んだ』(新潮文庫、2001年)
担当:川久保
2011年07月21日
リーダーの心得
皆さんこんにちは、株式会社シンプルウェイのウェブコンサルタント川久保です。
最近読んだ本(※)に、面白いことが書いてありました。
まずは、以下の2つの実験例を読んでみて下さい。
-------------------------------------------------------------------------------------
~実験1~
数十匹のラット(ラットA)をガラス瓶に一匹ずつ入れ、そのビンを水で満たした。
その結果、すぐに溺れ死ぬラットもいれば、60時間程泳いでから溺れ死ぬラットもいた。
そこで次に、別の数十匹のラット(ラットB)を用意し、それらを何度も捕まえ、数分間水噴射を浴びせてから逃がすことを繰り返した後で、上記と同様の実験をした。
すると今度は、すぐに溺れ死ぬラットは一匹もおらず、全部のラットが平均して60時間以上泳いだ。
~実験2~
まず、箱を二つ用意する。
・箱A:箱Bと連動して、自動的に電気ショックが止まる。
・箱B:側面のパネルを押すことによって電気ショックが止まる。
二匹の犬をそれぞれの箱に入れ、電気ショックを与える。
その結果、箱Bに入れた犬(犬B)は、自分でパネルを押して電気ショックを止めることを覚えたのに対し、箱Aに入れた犬(犬A)は、電気ショックが止まるまでひたすらじっと耐えるだけだった。
そこで次に、簡単に飛び越えられる低い壁で二つに仕切られた部屋を用意し、一方の部屋には電気ショックを流し、もう一方の部屋には流さないという仕組みにした。
犬Aと犬Bを電気ショックの流れる方の部屋に置いたところ、犬Bはすぐに壁を飛び越えて電気ショックを回避したのに対し、犬Aは電気ショックの流れる部屋でじっと我慢し続けた。
-------------------------------------------------------------------------------------------
この2つの実験結果には、共通点があります。
ラットAおよび犬A(A群)と、ラットBおよび犬B(B群)とでは、実験の結果に大きな差がありました。
この差を生じさせた要因、それは、「自分自身の置かれている環境を、自分の力で変えることができる」と認識しているかどうかである、と著者は述べています。
ラットBは、何度も逃げることができたという経験から、犬Bは、自分で電気ショックを止めることが出来たという経験から、「自分の力で多少なりとも結果を変えられる」ことを学び、A群よりも優れたパフォーマンスを発揮したのです。
人間についても、同じことが言えるのではないでしょうか。
何かしら与えられた役割があるとして、それを言われた通りにこなさなければならない場合と、自分なりにやり方を工夫する余地が与えられている場合とでは、その役割に対するやる気も、結果として発揮できるパフォーマンスも、全く違ってくるように思います。(違わないというのであれば、悲しきかな、人間はラットや犬以下であることを認めざるを得ないでしょう。)
人を動かす立場にあるリーダーは、ともすれば自分の思うように物事を進めるため、完全にマニュアルでメンバーを縛ってしまいがちです。
しかし、それによって生まれるのは型通りの結果にすぎず、本当の意味で良い結果を生むことはできません。
少し遠回りに思えるかもしれませんが、それぞれのメンバーに対し、可能な範囲で、本人の裁量の余地すなわち「自分の力で変えることができる」余地を与えることにより、メンバー一人ひとりのやる気とパフォーマンスを最大限に引き出すことができるのだということを、リーダーの立場にいる方々には忘れないでいて欲しいと思います。
※参考文献:シーナ・アイエンガー著『選択の科学 コロンビア大学ビジネススクール特別講義』(文藝春秋、2010年)
本日の担当:川久保
2011年07月11日
つくばFCレディースの試合がUstream生中継
こんにちは、シンプルウェイの大野です。
弊社・つくばちゃんねるが応援する「つくばFCレディース」の県リーグ首位決戦(@セキショウチャレンジスタジアム)のUstream生中継が決定しました!

つくばFCレディースは、女子リーグの最高峰の「なでしこリーグ」参入を目標に頑張っています。そのためには、県リーグの優勝が不可欠。今回はその県リーグの首位決戦です。
今回のUstream生中継に、私と川久保が実況?ゲスト?として参加させてもらうことになりました。当日、まともなコメントを言える自信はありませんが、勝利のためにしっかり応援したいと思います。
皆さんももしよろしければご覧ください。
また、つくばの方は是非会場まで足を運んでいただき、女子サッカーを体感してみてください。
7月17日(日)9:30頃から以下のアドレスで配信される予定です。
http://www.ustream.tv/channel/tsukubafc
弊社・つくばちゃんねるが応援する「つくばFCレディース」の県リーグ首位決戦(@セキショウチャレンジスタジアム)のUstream生中継が決定しました!

つくばFCレディースは、女子リーグの最高峰の「なでしこリーグ」参入を目標に頑張っています。そのためには、県リーグの優勝が不可欠。今回はその県リーグの首位決戦です。
今回のUstream生中継に、私と川久保が実況?ゲスト?として参加させてもらうことになりました。当日、まともなコメントを言える自信はありませんが、勝利のためにしっかり応援したいと思います。
皆さんももしよろしければご覧ください。
また、つくばの方は是非会場まで足を運んでいただき、女子サッカーを体感してみてください。
7月17日(日)9:30頃から以下のアドレスで配信される予定です。
http://www.ustream.tv/channel/tsukubafc