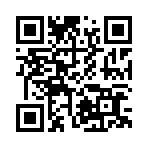2011年05月19日
著作権法講座(1) 著作権とは?
★今日の講座で出てくる条文:著作権法17条~28条
【はじめに】
皆さんこんにちは、シンプルウェイのウェブコンサルタント川久保です。
さて、著作権法講座の第1回目ということで、今日は著作権とはどんな権利かについてお話ししていこうと思います(^^)!
【総論】
まず、頭に入れておいて頂きたいのが、こちらの公式。
--------------------------------------------------------------
広義の著作権(17条)=著作者人格権(18~20条)+狭義の著作権(著作財産権)(21~28条)
--------------------------------------------------------------
ふだん何気なく使っている「著作権」という言葉ですが、著作権法が規定する著作権(広義)の中には、著作者人格権と狭義の著作権(著作財産権)が含まれている、というわけです。
【各論】
法律の条文を読むのは苦手!という方が大半かとは思いますが、
先ほどの公式のもととなる著作権法17条だけは、ちょっとチェックしておきましょう♪..
著作権法17条(著作者の権利) |
|---|
1 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 |
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 |
1項を見てみると、「公式の通りだなぁ」とお分かりいただけるのではないでしょうか?
ちなみに、2項は、著作者人格権や、(狭義の)著作権というのは、特許権などとは異なり、申請や手続きなどをしなくても、著作者であれば当然にそれらの権利を持っているんですよ、ということです。
それでは、著作者人格権・(狭義の)著作権とは、具体的にどんな権利なのか、さっそく見ていきましょう!
| 著作者人格権(18~20条) | |
|---|---|
| 公表権(18条) | 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利 |
| 氏名表示権(19条) | 著作物に著作者名を付するかどうか、付す場合には名義をどうするかを決定する権利 |
| 同一性保持権(20条) | 著作物の内容や題名を改変されない権利 |
| 狭義の著作権(著作財産権)(21~28条) | |
|---|---|
| 複製権(21条) | 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利 |
| 上演権及び演奏権(22条) | 著作物を公に上演し、演奏する権利 |
| 上映権(22条の2) | 著作物を公に上映する権利 |
| 公衆送信権等(23条) | 著作物を公衆に送信し、もしくは送信可能化し、あるいは公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利 |
| 口述権(24条) | 著作物を口頭で公に伝える権利 |
| 展示権(25条) | 美術の著作物または未発行の写真の著作物を公に展示する権利 |
| 頒布権(26条) | 映画の著作物を、その複製物の譲渡または貸与により公衆に提供する権利 |
| 譲渡権(26条の2) | 映画の著作物を除く著作物を、その複製物の譲渡により公衆に提供する権利(※一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には、譲渡権は及ばない。) |
| 貸与権(26条の3) | 映画の著作物を除く著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利 |
| 翻訳権・翻案権(27条) | 著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利 |
| 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条) | 翻訳物、翻案物等の原著作者は、これらの二次的著作物を利用する権利につき、これら二次的著作物の著作者と同一の権利を有する。 |
著作権について考える際には、まず、「著作権は著作権でも、具体的に上記のどの権利が問題となっているのか」を明らかにしましょう!
その上で、
「じゃあ、その権利は一体誰が有しているのか?」
「自分がやっていることは、誰かの権利を害していないか?」
などが問題となってくるのですが・・
それについては次回以降の講座で、ゆっくりじっくり理解していって頂ければと思います(^^)
それでは、次回をお楽しみに~
2011年05月13日
著作権法講座はじめます!
こんにちは、シンプルウェイの川久保です。
ウェブ関連のビジネスをする際に、避けて通れないのが著作権法。
ですが、法律を全く勉強したことがない方にとって、一から著作権法を学ぶのは至難の業ですよね。
そこで、法科大学院時代に受講した著作権法の授業のレジュメを、1講義分ずつ、分かり易くまとめてブログ記事にしていこうと思います!
ご期待ください(^^)
2011年05月12日
つくば生活は歩かない?

都内からつくばに引っ越された方が、つくばに来た後に太ったと言うのをよく耳にします。
都内は電車社会なので、家から駅まで歩いたり、駅から目的地に歩いたり、電車の乗り換えの時に階段を昇り降りしたり、気付かないうちにけっこう歩いているものです。それに比べてつくばは車社会なので、少しの距離でも車を使う人が多く、予想以上に歩いていないことが多いようです。
健康のためには1日1万歩以上歩くべきなんだそうです。
私の場合、1日つくばで過ごしたある日、1日の総歩数が2000歩程でした。
逆に都内で仕事をした日などは、1日少なくとも6000歩程度は歩いていました。ちなみに昨日は夕方には10000歩を超えました。
統計的なデータではないですが、つくばでの生活は意識して歩くことをしないと、都内での生活に比べて極端に歩くことが少なりそうです。
都内の人がつくばに来た時、とにかく街に人が歩いていないことに驚かれるケースが多いです。
つくばは商店街がないですし、お店とお店の距離が離れているので、車での移動が中心になってしまうのは仕方のないことなのかもしれません。
ただ、景観の統一をしたり、○○街と呼ばれるように同じジャンルのお店を集めたり、人を歩かせるような工夫が足りていないとも思います。開発が進んでしまった今から何ができるか、しっかり考えてみようと思います。
歩かせるのは無理があるような気もするので、そうなると自転車でしょうか…
2011年05月10日
ペットボトルのキャップについて
シンプルウェイの大野です。
前回はペットボトルを例にした話でしたが、今回はペットボトルのキャップについて書きたいと思います。
今回の震災では深刻なミネラルウォーター不足になりましたが、
キャップ工場の被災はもちろん、キャップの規格がバラバラだったことが増産できない理由の1つだったそうです。
最近ではキャップもオリジナルになっていますし、キャップにキャンペーン等のシールが貼ってあるものも多いですね。
(リサイクルの際は、キャップのシールを剥がさないといけないそうですよ。)
サントリーのサイトには、キャップの口径を大きくした理由がしっかり書かれています。
「サントリー天然水』の栓のサイズが他の製品より大きいのはどうしてですか?」
サントリーのものではないですが…

左:爽健美茶 右:Volvic

右のVolvicの方が口径が大きいのが分かります。
今回の震災がきっかけで、一定期間「無字無色で統一」するとのことです。
「全国清涼飲料工業会HPより」
ちなみに、口径等大きさの統一はなさそうです。大きさを統一させるためには、ボトル本体のラインも変える必要あるので現実的に無理なのだと思いますが。
他社商品と差別化することも大事ですが、危機管理や生産性のことを考えると規格を統一することも大事です。どちらにより重きをおくかは非常に難しい問題だと思います。
個人的には、全てを1つの規格にあてはめるのは難しいと思いますが、口径だけは何種類かに決めるなど、もう少し規格化した方がいいのでは、と思います。
ある程度限られた条件の中でも、知恵を絞れば他社商品との差別化・ブランド化を図ることは可能だと思います。
前回はペットボトルを例にした話でしたが、今回はペットボトルのキャップについて書きたいと思います。
今回の震災では深刻なミネラルウォーター不足になりましたが、
キャップ工場の被災はもちろん、キャップの規格がバラバラだったことが増産できない理由の1つだったそうです。
最近ではキャップもオリジナルになっていますし、キャップにキャンペーン等のシールが貼ってあるものも多いですね。
(リサイクルの際は、キャップのシールを剥がさないといけないそうですよ。)
サントリーのサイトには、キャップの口径を大きくした理由がしっかり書かれています。
「サントリー天然水』の栓のサイズが他の製品より大きいのはどうしてですか?」
サントリーのものではないですが…

左:爽健美茶 右:Volvic

右のVolvicの方が口径が大きいのが分かります。
今回の震災がきっかけで、一定期間「無字無色で統一」するとのことです。
「全国清涼飲料工業会HPより」
ちなみに、口径等大きさの統一はなさそうです。大きさを統一させるためには、ボトル本体のラインも変える必要あるので現実的に無理なのだと思いますが。
他社商品と差別化することも大事ですが、危機管理や生産性のことを考えると規格を統一することも大事です。どちらにより重きをおくかは非常に難しい問題だと思います。
個人的には、全てを1つの規格にあてはめるのは難しいと思いますが、口径だけは何種類かに決めるなど、もう少し規格化した方がいいのでは、と思います。
ある程度限られた条件の中でも、知恵を絞れば他社商品との差別化・ブランド化を図ることは可能だと思います。
2011年05月09日
「八風吹けども動ぜず」

皆さんこんにちは、シンプルウェイの川久保です。
日本人の多くの方がそうであるように、特定の宗教を深く信仰してはいない私ですが、
古くからある宗教が、どのような思想に基づいているのかには興味があるので、
留学生の友人に、その国で広く信仰されている宗教についての話を聞いたり、
仏教やキリスト教などに関連する書物を軽く読んだりはしています。
何世紀にもわたって、多くの人に支持されてきただけあって、
それぞれの宗教の教えの中には、考え方として私達の日常生活に役立つものも多々あります。
今日は、禅宗の「寒山詩」の中から、
一つ、私が個人的に気に入っている言葉をご紹介しようと思います。
「八風吹不動 (八風吹けども動ぜず)」
「八風」とは、人の心を乱す八つの逆風(利・衰・毀・誉・称・譏・苦・楽)を指します。
●利は、自分の意にかなうこと。
●衰は、自分の意にかなわないこと。
●毀は、影で悪口を言われること。
●誉は、影で褒められること。
●称は、目の前で称賛されること。
●譏は、目の前で誹られること。
●苦は、心身を悩ますこと。
●楽は、心身を喜ばすこと。
この言葉で最も興味深いのが、
「衰・毀・譏・苦」というネガティブな要素のみならず、
「利・誉・称・楽」というポジティブな要素も
人の心を乱す逆風の中に含まれているという点です。
ビジネスで成功した、試験に合格した、子宝を授かった・・・
仕事でもプライベートでも、ポジティブな出来事が起きること
それ自体はとても素晴らしいことです。
しかし、
そんな時、つい有頂天になり、
周りのこと・今後のことを考えずに、軽はずみな言動をとってしまいがちであることも、
また事実だと思います。
「利・誉・称・楽」も、「八風」に含まれているということをしっかりと肝に銘じて、
「衰・毀・譏・苦」な状態の場合はもちろん、
「利・誉・称・楽」な状態の自分も、
きちんとコントロール出来るようになりたいものです。
2011年05月08日
商品・サービスの差別化の重要性
シンプルウェイの大野です。
ペットボトルを捨てるときにパッケージを取り外すのが面倒なので、買った後すぐにパッケージを剥がしてしまうのですが、
パッケージがある・なしを比べると味の美味しさまで変わるような気がしました。

皆さんはどうですか?
やはりパッケージやパッケージデザインは大事ですよね。
「い・ろ・は・す」などは、売り上げにコンセプト・プロダクトデザインがかなり大きく寄与していると思います。
多種多様な商品が次々に市場に出てくる今の時代で勝ち抜くためには、味だけではなく、コンセプトづくり、プロダクトデザインづくり、その背景にある物語が非常に大事になると思います。
自社の商品・サービスに、同業他社のものにはない魅力がありますか?
万人に支持される商品・サービスを目指すことも大事ですが、小さな企業・お店が勝ち残っていくためには、ある特定層にピンポイントで魅力を伝え、コアなファンを獲得することがもっと大事だと私は思います。
まずは消費者目線で自社の商品を評価してみましょう。
ペットボトルを捨てるときにパッケージを取り外すのが面倒なので、買った後すぐにパッケージを剥がしてしまうのですが、
パッケージがある・なしを比べると味の美味しさまで変わるような気がしました。

皆さんはどうですか?
やはりパッケージやパッケージデザインは大事ですよね。
「い・ろ・は・す」などは、売り上げにコンセプト・プロダクトデザインがかなり大きく寄与していると思います。
多種多様な商品が次々に市場に出てくる今の時代で勝ち抜くためには、味だけではなく、コンセプトづくり、プロダクトデザインづくり、その背景にある物語が非常に大事になると思います。
自社の商品・サービスに、同業他社のものにはない魅力がありますか?
万人に支持される商品・サービスを目指すことも大事ですが、小さな企業・お店が勝ち残っていくためには、ある特定層にピンポイントで魅力を伝え、コアなファンを獲得することがもっと大事だと私は思います。
まずは消費者目線で自社の商品を評価してみましょう。
2011年05月02日
HPなどで使う写真撮影
シンプルウェイの大野です。
先日、ホームページなどで使うための写真をカメラマンの方に撮っていただきました。

写真の善し悪しで、閲覧者に与える印象はかなり変わります。
そうお客様に伝え続けてきたのにも関わらず、自社のホームページ等では自分たちで撮った写真のままという状況でした。
人も増えてきましたし、ホームページのリニューアルも考えているので、プロのカメラマンに撮影を依頼をしました。

弊社の和気あいあいとした雰囲気と、自然に囲まれたつくばオフィスと、「やる時はしっかりやる」といった感じが伝わる写真が撮れたのではないかと思います。
このコンサルタントブログも、1ヵ月程でリニューアルします。
そのホームページでは、今回撮影した写真を使いますのでお楽しみに。
先日、ホームページなどで使うための写真をカメラマンの方に撮っていただきました。

写真の善し悪しで、閲覧者に与える印象はかなり変わります。
そうお客様に伝え続けてきたのにも関わらず、自社のホームページ等では自分たちで撮った写真のままという状況でした。
人も増えてきましたし、ホームページのリニューアルも考えているので、プロのカメラマンに撮影を依頼をしました。

弊社の和気あいあいとした雰囲気と、自然に囲まれたつくばオフィスと、「やる時はしっかりやる」といった感じが伝わる写真が撮れたのではないかと思います。
このコンサルタントブログも、1ヵ月程でリニューアルします。
そのホームページでは、今回撮影した写真を使いますのでお楽しみに。